厳しい修行に耐えて,十両・幕内を目指す大相撲界の力士たち。
この相撲の世界の給与体系、懸賞金、三賞、金星・銀星について詳しく説明します。
あわせて読みたい


大相撲 令和八年初場所の新番付予想 新大関・安青錦 新三役は?
大相撲九州場所は千秋楽の優勝決定戦で安青錦が豊曻龍を破り,初優勝を飾るとともに,大関昇進を確実にして幕を閉じました。 ますます高まる相撲熱。秋場所を終えた時点...
目次
階級別の給与体系
力士の階級(番付)は、**関取(十両以上)と力士養成員(幕下以下)**で待遇が大きく異なります。
関取(横綱〜十両)の固定給
| 階級 | 月給(目安) |
| 横綱 | 300万円 |
| 大関 | 250万円 |
| 関脇・小結 | 180万円 |
| 前頭 | 140万円 |
| 十両 | 110万円 |
賞与(ボーナス): 月給の1ヶ月分が年2回(9月、12月)支給されます。
- 場所手当(特別場所手当): 本場所ごとに支給されます(例:横綱20万円、大関15万円、関脇・小結5万円など)。
- 力士報奨金(給金):
- 十両以上の力士に、場所ごとに支給される「第2の給与」とも言えるものです。
- 計算式は「持ち給金 × 4000円」です。
- 持ち給金は、序ノ口で3円からスタートし、勝ち越し1点につき0.5円、幕内優勝30円(全勝優勝50円)、金星1個につき10円が加算されていく、現役中の功績の累計です。
力士養成員(幕下〜序ノ口)の待遇
- 月給: ありません。
- 場所手当: 年6回の本場所ごとに支給されます(例:幕下16.5万円、序ノ口7.7万円など)。
- 衣食住は相撲部屋で面倒を見てもらえます。
懸賞金(けんしょうきん)の仕組みと税金、配分
懸賞金は、企業などが特定の取組に対してかける金銭です。
仕組みと配分
- 1本当たりの金額: 1本あたり70,000円(税込)です。(2019年9月場所から改定)
- 内訳:
- 勝ち力士の獲得金額: 60,000円
- 日本相撲協会手数料(取組表掲載料・場内放送料): 10,000円
- 勝ち力士が受け取る金額: 60,000円のうち、30,000円が力士の手取りとなります。
- 残りの30,000円は、力士の所得税の預かり金(一時預かり金)として日本相撲協会がプールし、力士の引退時などに「退職金」の一部としてまとめて支払われます。
税金
- 所得区分: 懸賞金は力士の事業所得として課税されます。
- 一時所得とは異なり、経費を差し引いた後の利益に対して課税されます。

三賞(殊勲賞・敢闘賞・技能賞)の賞金額
三賞は、関脇以下の幕内力士が本場所で優秀な成績を収めた際に選考委員会によって授与されます。
- 賞金: 各賞につき200万円。
- 一人の力士が複数の賞を同時受賞した場合は、受賞した賞の数だけ賞金が加算されます(例:2賞受賞で400万円、3賞受賞で600万円)。
- 複数の力士が同じ賞を受賞した場合も、それぞれに200万円が支給されます。
金星・銀星の仕組みと賞金
金星(きんぼし)
- 定義: 平幕(前頭)の力士が横綱を破ること。
- 賞金・仕組み:
- 金星そのものに対する現金の賞金はありませんが、力士の持ち給金が増えるという形で生涯にわたる収入増につながります。
- 金星1個につき、力士報奨金の計算基準となる持ち給金が10円加算されます。
- これにより、現役中、休場しない限り、毎場所の報奨金が**10×4000円=40,000円**ずつ増額されます。
銀星(ぎんぼし)
- 定義: 平幕(前頭)の力士が大関を破ること。
- 賞金・仕組み:
- 銀星は、金星のような持ち給金の特別加算の制度はありません。
- 一般的に、金星と区別するために用いられる呼称で、報奨金制度上の特別な賞金はありません。
むすび
このように、大相撲の世界は、番付を頂点とする厳格なヒエラルキーのもと、独自の経済システムが成り立っています。
関取と力士養成員の間には月給の有無という「天国と地獄」ほどの大きな差があり、力士は絶えず昇進を目指します。給与体系においては、月給だけでなく、過去の功績が積み重なる報奨金(持ち給金)が、現役期間を通して収入を大きく左右する重要な要素となっています。
また、懸賞金は華やかな勝利の証でありながら、その税制と積立の仕組みは、力士の将来の所得を保障するシステムとしても機能しています。さらに、三賞や金星は、単なる名誉に留まらず、それぞれが多額の賞金や生涯にわたる報奨金の増額という形で、力士の努力に報いる構造になっています。
大相撲の収入体系は、単なる固定給ではなく、「地位は実力次第」という角界の厳しさと、努力と勝利が直接的に経済的な安定につながる独自の仕組みを体現していると言えるでしょう。

あわせて読みたい


大相撲界の近況報告 安青錦・大の里・義ノ富士は 照ノ富士の引退相撲も
現在(2025年12月中旬)、大相撲界では冬巡業が各地で開催されており、来年1月の初場所(一月場所)に向けた動きが活発になっています。 おもなトピックス 1. 安青錦(...





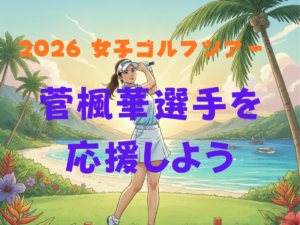
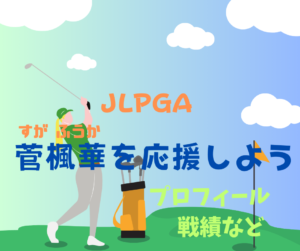



コメント