最近、「ガソリン暫定税率の廃止」というニュースを耳にすることが増えましたね。でも、「暫定税率って何?」「廃止されたら、結局ガソリン代は安くなるの?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
今回はこの複雑な税制の話を、私たち普通の人が分かりやすく理解できるように解説します。暫定税率の基本的な仕組みから、廃止によって私たち市民の生活にどんなメリットやデメリットがあるのかを、詳しく見ていきましょう。
1. そもそも「ガソリン暫定税率」って何?
ガソリンには、「ガソリン税(揮発油税および地方揮発油税)」という税金がかかっています。このガソリン税は、実は「本則税率」と「暫定税率」の二重構造になっています。
ガソリン税の仕組み
| 税率の種類 | 役割と金額 |
| 本則税率 | ガソリン1リットルあたり 28.7円。本来の恒久的な税率です。 |
| 暫定税率 | ガソリン1リットルあたり 25.1円。本則税率に上乗せされている部分です。 |
| 合計 | ガソリン税の合計額は 53.8円 となり、このうち約半分が暫定税率による上乗せということになります。 |
なぜ「暫定」なのに長く続いたの?
この「暫定税率」は、もともと1974年に「道路整備の財源確保」を目的として,一時的な措置として導入されました。しかし、その後も道路網の拡充や国の財政需要を理由に延長が繰り返され、約50年近くにわたって実質的に「恒久的な増税」として徴収され続けてきました。
2009年には道路特定財源制度が廃止され、暫定税率分も一般財源(使い道が特定されない国の予算)に組み入れられましたが、税率自体は「特例税率」と名前を変えながらも維持されてきた、というのがこれまでの経緯です。
2. 暫定税率廃止が実現するとどうなる?
与野党間の協議の結果、ガソリンの暫定税率は2025年12月31日をもって廃止される方向で合意されました(軽油引取税の暫定税率は2026年4月1日に廃止予定)。
廃止が実現した場合、最も大きな影響はガソリン価格の低下です。
価格への影響は
ガソリン1リットルあたり、上乗せされていた暫定税率25.1円と、それにかかっていた消費税分(約2.5円)の合計、約27.6円が恒久的に引き下げられることになります。
ただし、現在進行形で政府が実施しているガソリン価格を抑えるための補助金(約10円〜20円)は、暫定税率廃止に合わせて段階的に縮小・廃止される見込みです。そのため、廃止直後に「約27.6円」が一気に値下がりするわけではなく、補助金がなくなった分と暫定税率が廃止された分の差し引きで、最終的な値下げ幅が決まります。
例: 現在の価格(補助金込み)が170円だと仮定すると、補助金が完全に廃止され、暫定税率も廃止された後の価格は、単純計算で170円 – (27.6円 – 補助金分) となり、補助金が約10円だった場合、実質約17.6円程度の値下げ効果が見込まれます。
3. 市民にとってのメリット(家計と経済)
暫定税率の廃止は、特にマイカーを利用する一般市民の生活に、以下のようなメリットをもたらします。
メリット1: 家計負担の恒久的な軽減
最も分かりやすいメリットは、ガソリン代の節約です。
- 自家用車を頻繁に利用する世帯、特に公共交通機関が少ない地方に住む人々にとって、毎月の支出が抑えられます。
- 平均的な家庭で年間数千円から1万円以上の負担軽減につながるとの試算もあります。
メリット2: 物流コストの削減と物価の安定
ガソリン価格の低下は、自家用車だけでなく、トラックやバスなどの運送業のコストも引き下げます。
- 物流コストが下がれば、企業はその分を価格に転嫁する必要がなくなるため、商品の価格上昇を抑える効果が期待できます(物価の安定)。
- タクシーやバスの運賃など、公共交通機関のコストにも良い影響がある可能性があります。
メリット3: 地方経済・観光業の活性化
ガソリン代が安くなると、旅行やドライブのハードルが下がります。
- 自家用車での長距離移動が増え、特に地方の観光地へのアクセスが促進されます。
- 宿泊施設や飲食店、観光関連産業の売上増加につながり、地方経済の活性化が期待できます。

4. 市民にとってのデメリット・課題(社会と財政)
一方で、暫定税率の廃止は、国の財政や環境問題など、社会全体に関わる大きな課題も抱えています。
デメリット1: 巨額の税収減による財源不足
暫定税率が廃止されると、国と地方自治体合わせて年間約1兆円~1.5兆円もの巨額の税収が失われます。
- この税収は、現在、道路の整備・維持管理だけでなく、医療、教育、子育て支援など、幅広い一般財源として使われています。
- 税収が不足すると、公共サービスやインフラの維持管理に必要な財源が不足し、その質が低下する恐れがあります。
デメリット2: 代替財源の確保と国民負担の増加リスク
失われた税収を補うために、政府は新たな財源を確保する必要があります。
- 財源不足を補填するために、他の税の増税(例:消費税など)や、新たな税の創設が検討される可能性があります。
- 結果として、ガソリン代で減った負担が、形を変えて国民全体に重くのしかかるリスクも指摘されています。
デメリット3: 脱炭素社会への逆行の懸念
世界的に地球温暖化対策として「脱炭素社会」への移行が進められています。
- ガソリン価格が下がると、ガソリン車の利用が増え、消費が促進される可能性があります。
- これは、化石燃料の使用を減らすという環境保護の流れに逆行するという懸念を引き起こします。
まとめ:賢くメリットを享受し、課題に目を向ける
ガソリン暫定税率の廃止は、私たち消費者にとって家計負担を恒久的に軽減するという大きなメリットがあります。特に物価高騰に苦しむ現在、その恩恵は無視できません。
しかし、その裏側には年間1兆円を超える税収減という大きな課題が隠れています。この税収減が、将来的にどのような形で私たちの社会サービスや他の税負担に影響してくるのか、注意深く見守る必要があります。
私たちは、ガソリン価格の動向だけでなく、政府が今後どのように代替財源を確保し、公共サービスを維持していくのかについて、引き続き関心を持ち続ける必要があるでしょう。



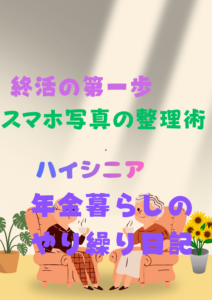

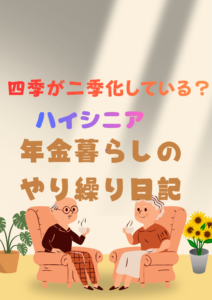

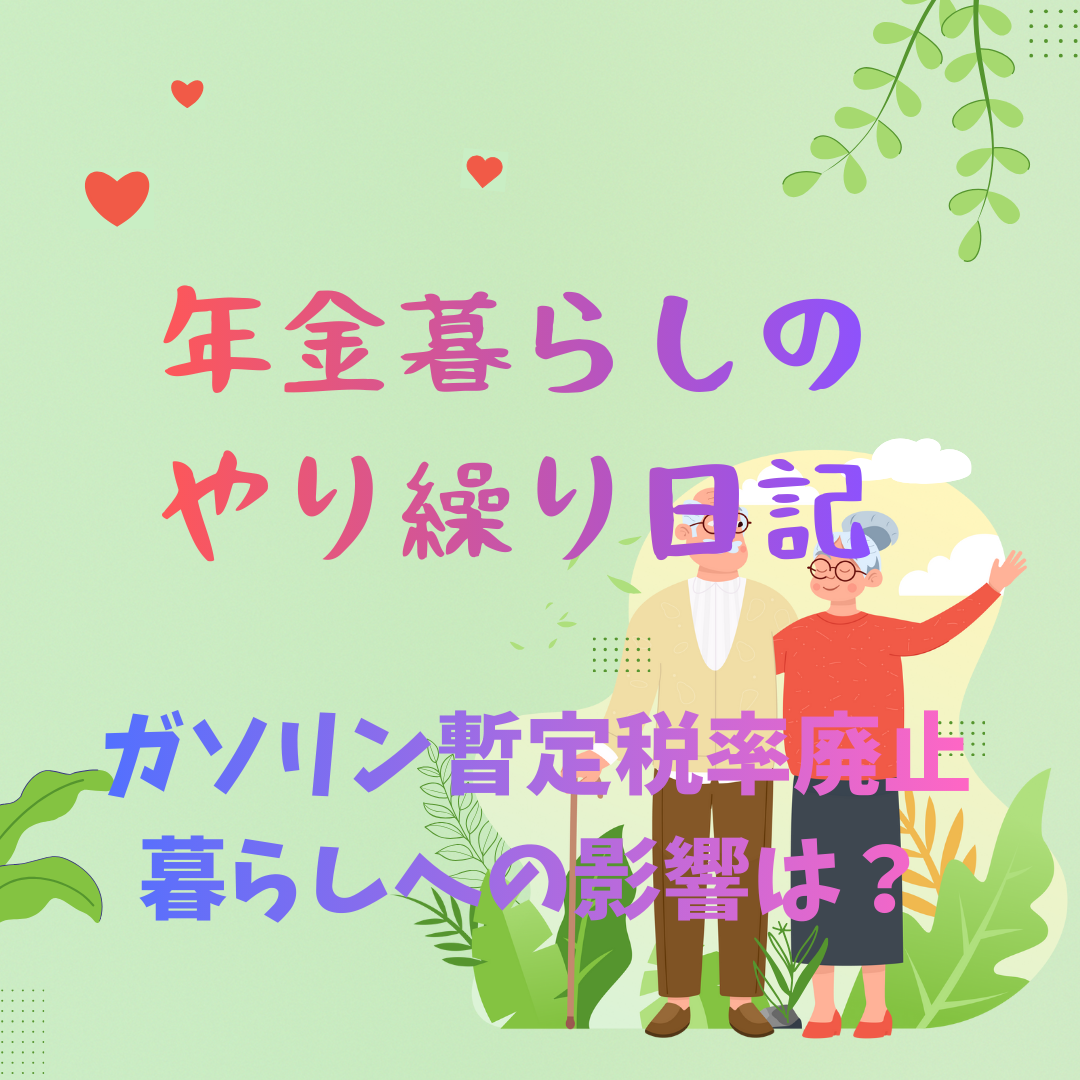




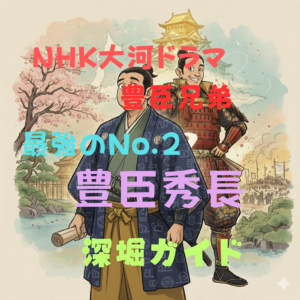
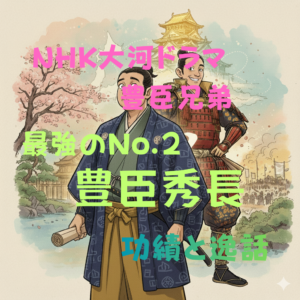
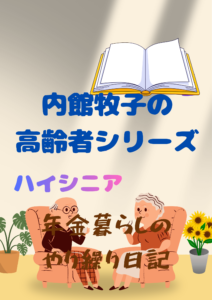
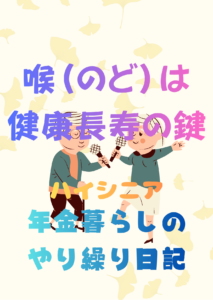
コメント